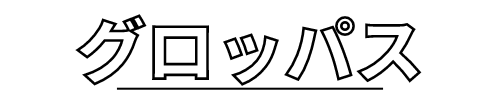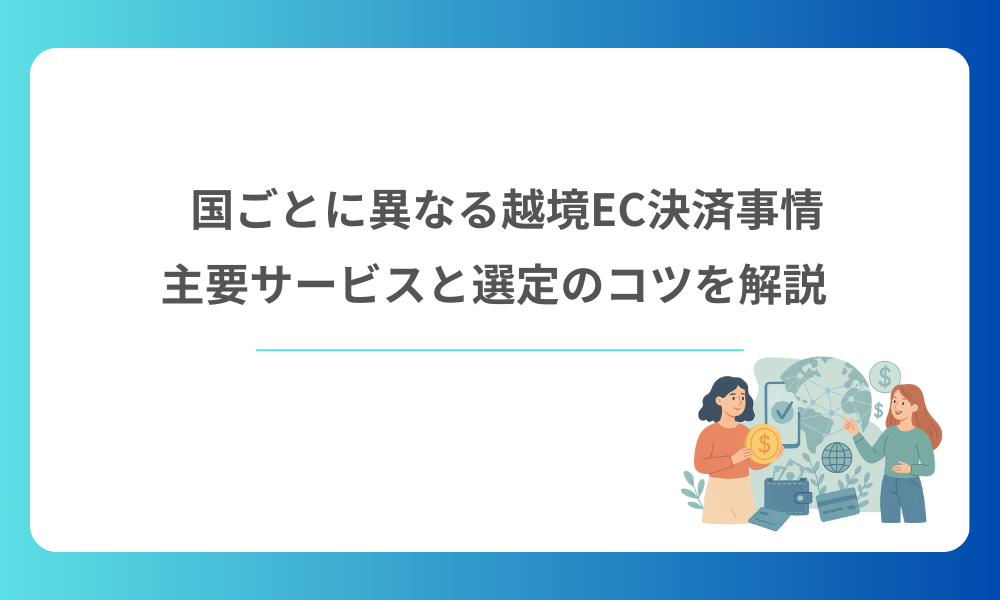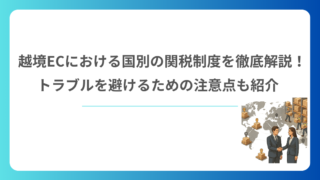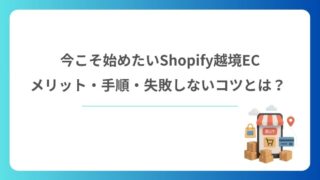越境ECを立ち上げる、あるいはすでに展開している事業者にとって、決済手段の選び方は売上や顧客満足度に大きく影響します。国や地域ごとに主流の決済方法は異なるため、自社の商材やターゲット市場に適した手段を選定しなければ、購入の機会を逃すおそれがあります。
そこで今回は、代表的な越境EC決済の種類や地域別の傾向、さらに選定時の比較ポイントについても解説します。スムーズな決済環境を整えたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ越境ECにおいて決済方法が重要なのか

越境ECにおいて決済手段の選定は、販売機会の損失を防ぎ、ユーザーの信頼を得るために欠かせない要素です。国や地域によって、消費者が日常的に利用している決済方法は異なり、日本国内で一般的な手段が通用しない場合もあります。
たとえば中国ではAlipayやWeChat Payが、アメリカではPayPalやクレジットカードが主流であり、こうした現地の習慣を無視した決済方法しか用意していないと、購入を途中でやめてしまう利用者が増えるおそれがあります。
さらに、多くのユーザーは初めて訪れるECサイトに慎重な姿勢を示すため、信頼性やセキュリティへの不安が拭えない場合、購入を見送る傾向も否めません。そのため、ターゲットとする国や地域において支持されている決済手段をあらかじめ調査し、適切に導入することが、売上拡大の基盤を築く第一歩となります。
越境ECで利用される主な決済手段

越境ECでは、購入者の多様なニーズに応えるために、現地で普及している決済手段を適切に選ぶことが重要です。国や地域によって主流の決済方法は異なるため、事前にターゲット市場を把握し、自社に最適な手段を導入する必要があります。
ここでは、越境ECで代表的に利用される各種決済方法の特徴と活用のポイントをご紹介します。
クレジットカード決済:世界的に標準の決済手段
クレジットカード決済は、越境ECにおいて最も一般的で広く受け入れられている方法の一つです。Visa、Mastercard、American Expressなどの国際ブランドは多くの国と地域で使用され、特にアメリカやヨーロッパでは高い利用率を誇ります。
事業者側にとっては、確実な代金回収が可能であり、売上の管理もしやすいという利点があります。購入者にとっても、慣れ親しんだ決済手段を選べることで心理的な障壁が下がり、カゴ落ちの防止にも効果的です。不正利用によるチャージバックといったリスクも存在しますが、適切なセキュリティ対策を講じれば一定の軽減が期待できます。
さらに、多通貨決済や分割払いに対応するカードも多く、国際取引との親和性が高いため、越境ECでは導入を前提とすべき決済手段といえるでしょう。
デビットカード:リアルタイム引き落としで信頼性が高い
デビットカードは、購入と同時に銀行口座から代金が即時引き落とされる仕組みで、後払いのクレジットカードと比べて支出を把握しやすく、利用者に安心感を与える決済手段といえます。
アメリカや韓国をはじめ、一部の国ではクレジットカードに次ぐ利用率を誇り、越境ECでも信頼性の高い選択肢として注目されています。事業者にとっても、未回収のリスクが低く、チャージバックが発生しにくいという点で導入メリットが大きいです。
さらに、クレジットカードを保有していない若年層にもリーチできるため、新たな顧客層の獲得にもつながります。対応ブランドが幅広く、導入コストも比較的抑えられることから、ターゲット国のニーズに応じて柔軟に運用できる点も魅力です。
第三者支払いサービス(PayPalなど):手軽で信頼感が高い
第三者支払いサービスは、越境ECにおいて信頼性の高い決済手段として広く利用されています。中でも代表的なPayPalは、消費者と事業者の間に決済事業者が介在する仕組みにより、カード情報や銀行口座の詳細を直接サイト側に提供せずに決済を完了できます。
この構造がプライバシー保護とセキュリティ強化につながり、初めて利用する海外サイトでも安心して取引ができると感じる利用者が多くいます。事業者側にとっては、導入が比較的容易で、国際決済への対応力を高める手段として有効です。
さらに、PayPalは200以上の国と地域で展開され、世界で3億人以上に利用されており、グローバル市場へのアクセスを拡大したい企業にとって強力な後押しとなります。とくに欧米市場を重視する場合には、優先的な導入を検討する価値があるといえるでしょう。
電子マネー:東アジア圏での利用率が高いキャッシュレス決済
電子マネーは、あらかじめチャージして使うプリペイド式と、決済後に口座から引き落とされるポストペイ式の2種類に分かれます。スマートフォンやICカードを利用した手軽な決済手段として、東アジア圏を中心に広く普及してきました。
たとえば日本ではSuicaや楽天Edy、韓国ではT-money、台湾ではLINE Payが代表的です。こうした電子マネーは、少額の買い物や日常的な支払いによく用いられています。ただし、越境ECでの導入にあたっては、国や地域ごとに利用率の差が見られるため、導入の優先度はターゲット市場の特性に左右されます。
とくに若年層の間ではキャッシュレス志向が高まっており、電子マネーへの対応は利便性と安心感の提供につながります。 結果として購入離脱の抑制にも効果があり、現地の消費行動に即した対応が売上拡大の一因となります。
ネットバンキング/口座振込:東南アジア・欧州での実用性
ネットバンキングや口座振込は、シンプルで信頼性のある決済手段として、東南アジアや欧州の一部地域で広く利用されています。特にマレーシアやタイでは、モバイルバンキングの浸透により、手数料なしで即時送金が可能となり、越境ECにおいても銀行送金の活用が進んでいます。
欧州では、ドイツやオランダなどでクレジットカードよりも銀行振込を好む消費者が多く、堅実な決済方法として根強い支持を得ています。導入時には、現地通貨による口座管理や為替対応といった課題も想定されますが、地域に特化した決済代行サービスを活用すれば対応が可能です。
法人取引やカード非保有層を意識した販売展開においても、有効な選択肢といえるでしょう。
代金引換:ローカル市場で根強く残る選択肢
代金引換は、商品受け取り時に現金で支払うシンプルな決済方法です。クレジットカードや電子マネーが浸透する現在でも、特定のローカル市場では根強い支持を集めています。特に台湾や東南アジアの一部地域では、「商品を確認してから支払いたい」という消費者心理が根強く、信頼性のある手段として選ばれる傾向があります。
オンライン決済に不安を感じる層やクレジットカードを保有していない顧客にも対応できるため、ターゲット市場によっては有効な選択肢となります。一方で、国際配送に対応しているかどうか、手数料の発生、現地物流業者との連携体制など、実装には慎重な検討が必要です。
導入を検討する際には、対象国の文化的背景や購買傾向を十分に理解し、それに沿った対応を取ることが求められます。
国別に見る越境EC決済の主流手段

越境ECを成功させるためには、現地ユーザーが普段から使い慣れている決済手段を導入することが欠かせません。国や地域ごとに主流の決済方法は異なり、適切な選定を怠ると販売機会を逃す恐れもあります。
ここでは、中国・アメリカ・東南アジアなど主要地域で支持されている決済手段の特徴や利用傾向について解説します。
| 地域・国 | 主な決済手段 | 特徴・傾向 | EC利用者に人気の理由 |
|---|---|---|---|
| 中国 | Alipay・WeChat Pay・銀聯カード | QRコード決済と銀聯カードが広範に普及 | 即時決済と高い利便性、個人情報の保護が評価されている |
| アメリカ | PayPal・クレジットカード | クレジットカード文化が根強く、PayPalの信頼性も高い | 利便性とセキュリティを兼ね備え、購入者の安心感が高い |
| 東南アジア | GrabPay・ShopeePay | スマホによるQR決済が普及し、地域特化型サービスが急成長 | 手軽さと低コスト、若年層にも広く浸透 |
| 台湾・香港 | クレジットカード・LINE Pay・Apple Pay | カードと電子マネーの併用が一般的 | 多様な選択肢があり、ライフスタイルに合わせやすい |
| 韓国 | Kakao Pay・Naver Pay | モバイル決済が日常生活に密着 | ポイント還元や即時性、利便性の高さから高支持 |
中国:Alipay・WeChat Pay・銀聯カードが主流
中国における越境ECでは、「Alipay(アリペイ)」「WeChat Pay(ウィーチャットペイ)」「銀聯カード(UnionPay)」が主要な決済手段として広く利用されています。中でもAlipayとWeChat Payは、QRコードを用いたモバイル決済の先駆けとなり、中国国内で圧倒的な普及を見せています。
キャッシュレス化を推進する原動力ともなっており、日常生活に深く根付いているのが特徴です。一方、銀聯カードはクレジット機能とデビット機能の両方を備えた国際ブランドとして、実店舗およびオンライン決済の両面で高い利便性を発揮しています。
これらの手段はいずれも即時性が高く、情報の保護面でも信頼性が確立されています。現地の消費者にとって使い慣れており、安心して選べることが、購買を後押しする最大の理由となっています。
アメリカ:PayPalとクレジットカードが圧倒的
アメリカは越境ECの主要ターゲット国の一つであり、決済手段として「クレジットカード」と「PayPal」が高い支持を得ています。VisaやMastercardなどの国際ブランドは広く浸透しており、とくにクレジットカードは日常的なオンラインショッピングで一般的に用いられています。
一方、PayPalは第三者支払いサービスとして信頼性が高く、カード情報を直接入力せずに取引できる点が評価されています。これらの決済手段は利便性とセキュリティを兼ね備えており、購入者に安心感を与えるものです。アメリカ市場を視野に入れるうえで、いずれの導入も避けては通れない要素といえるでしょう。
東南アジア:GrabPayやShopeePayなどのローカル決済が急成長
東南アジアではモバイル端末を活用したローカル決済の導入が急速に進み、GrabPayやShopeePayなど地域に根ざしたサービスが越境EC市場でも存在感を強めています。マレーシアやインドネシア、フィリピンなどでは、QRコードを用いたスマートフォン決済が普及しており、現金やクレジットカードに代わる主要な支払い手段となりつつあります。
これらの決済方法は、手軽で手数料も抑えられることから、クレジットカードを持たない若年層を中心に幅広く利用されています。加えて、ShopeeやGrabといった現地大手サービスとの連携により、購買から決済までがシームレスにつながるユーザー体験が提供されている点も魅力といえるでしょう。
東南アジア市場を視野に入れる際は、こうしたローカル決済への対応を検討することが欠かせません。
台湾・香港:クレカ決済と電子マネーが並行して定着
台湾・香港では、クレジットカードと電子マネーの両方が広く利用されており、越境ECの現場でも両者の併用が一般的となっています。VisaやMastercardなど国際ブランドのカード決済は特に台湾で主力の支払い手段とされ、高い普及率を誇ります。
一方、LINE PayやApple Payといった電子マネーも日常生活に深く根付いており、少額決済やスマートフォンとの連携に優れる点が注目されています。加えて、台湾ではコンビニ決済や代金引換も一定の支持を集めており、香港ではAlipayHKなど地域特化型のモバイル決済サービスが存在感を示しています。
こうした多様な手段が並存することで、利用者は自身のライフスタイルに合った方法を柔軟に選ぶことができ、結果として購買意欲の促進にもつながっています。
韓国:Kakao PayやNaver Payが主流に
韓国ではキャッシュレス決済が非常に普及しており、越境ECにおいても「Kakao Pay(カカオペイ)」や「Naver Pay(ネイバーペイ)」といったモバイル決済サービスが主な手段として定着しています。
これらのサービスは、SNSや検索ポータルといった日常的に使用されるプラットフォームと連携しており、ユーザーはアプリ内でスムーズに支払いを完了できます。また、韓国はクレジットカードの普及率が高く、オンラインでの決済に対する抵抗感が少ない点も特徴です。そのため、複数のキャッシュレス手段が併用される傾向があります。
Kakao PayやNaver Payは、ポイント還元や即時決済などの利便性に優れ、特に若年層から支持を集めています。こうした利用のしやすさと信頼性の高さが、現地ユーザーの継続的な利用を促しており、越境ECの成功を左右する重要な要素となっています。
越境EC決済サービスの選び方と比較ポイント

越境ECで成功を目指すには、対象国に合った決済手段を選定することが欠かせません。ユーザーの購買行動や信頼性に直結するため、導入前の比較検討は慎重に行う必要があります。
ここでは、決済サービス選びの視点と評価すべきポイントを詳しく解説します。
ターゲット国の主流決済手段に対応しているか
越境ECの成否を左右する要素のひとつが、ターゲット国で広く利用されている決済手段への対応状況です。各国の消費者は、普段使い慣れている支払い方法でなければ購入に不安を感じやすくなります。
たとえば中国ではAlipayやWeChat Pay、アメリカではクレジットカードやPayPalが主流とされ、台湾ではコンビニ払いが定着し、東南アジアではShopeePayやGrabPayなどの地域特化型サービスが支持を集めています。これらの決済手段は利便性や信頼性の高さに加え、日常的に利用するアプリと連携している点が選ばれる理由です。
一方で日本国内向けに慣れた決済方法だけを採用すると、現地ユーザーとの接点を失う恐れがあります。 販売機会を逃さないためにも各国の決済習慣を十分に調査し、ユーザーが安心して購入に進める環境を構築することが求められます。 導入時には、地域ごとの主流手段とその背景にある利用特性を把握し、実際の利用シーンを想定した対応が必要です。
自社商品の単価・販売モデルに合っているか
越境ECで決済手段を選定する際には、ターゲット国の利用傾向だけでなく、自社商品の単価や販売モデルとの相性も考慮する必要があります。たとえば高単価の商品を取り扱う場合には、クレジットカードや分割払いに対応している決済手段が適しており購入者の支払負担を軽減できます。
このような配慮は、購入をためらう要因を減らすうえでも重要です。一方、若年層向けや低価格帯の商品では、デビットカードやモバイル決済、電子マネーのように、利便性を重視した手段のほうがスムーズな購買体験を実現しやすくなります。
さらに、定期購入モデルを採用している場合には、口座振替や後払いに対応することで、継続率の向上にもつながります。販売形態に応じた決済手段を取り入れることで、売上の最大化と顧客満足度の向上が見込めます。
手数料・為替コスト・入金サイクルは妥当か
越境ECにおける決済手段の選定では、導入時の初期費用だけでなく、決済手数料や為替コスト、入金サイクルといった運用上の条件についても慎重に見極める必要があります。たとえば、クレジットカード決済は多くの国で一般的に利用されている一方で、売上の3〜4%程度の手数料が発生します。
さらに、外国通貨による取引では、為替手数料や両替時のレート変動により利益が圧迫されるおそれがあります。入金までの期間が長い場合には、キャッシュフローに影響が出ることもあり、事業の安定性を左右する要因となり得ます。
各国・地域ごとに決済サービスの条件は異なるため、導入前に複数の選択肢を比較したうえで、自社の販売モデルに最適な手段を選ぶことが重要です。
セキュリティ・チャージバック対策は万全か
越境ECにおいては、セキュリティ対策とチャージバックの防止策を徹底することが欠かせません。とくに海外発行のクレジットカードを用いた決済では、不正利用や情報漏えいのリスクが高まるため、3Dセキュアなどの本人認証を導入して安全性を強化する必要があります。
加えて、チャージバックは売上の取消や事業者側の手数料負担につながる可能性があるため、取引履歴の保存や不審な注文の自動検出機能を整備しておくことが望ましいです。さらに、信頼性の高い決済代行サービスを利用すれば、国際的なセキュリティ基準(PCI DSSなど)を満たした環境のもとで決済を処理でき、顧客の安心感にも寄与します。
こうした対策を自社で講じると同時に、専門サービスを適切に組み合わせることが、越境ECを安定的に運営するうえでの重要なポイントとなります。
決済代行サービスの活用で運用負担を軽減できるか
越境ECでは、国ごとに異なる決済手段への対応や契約管理が複雑化しやすく、運用面での負担が増す傾向にあります。こうした課題に対する有効な解決策として、決済代行サービスの導入が挙げられます。
各国で主流とされる決済方法を一括して導入・管理できるため、個別契約の手間や関連コストの削減が期待できます。加えて、複数通貨の自動換算機能や入金管理の一元化にも対応しているサービスが多く、経理業務の効率化にもつながります。
不正決済やチャージバックへの対応、セキュリティ体制の強化といったリスク対策も任せられるため、限られたリソースの中で越境ECを運営する企業にとっては、非常に心強い支援となるでしょう。
越境EC決済サービスを導入する前に確認しておきたい注意点

越境ECにおける決済手段の選定では、導入後の運用リスクにも目を向ける必要があります。為替変動や関税、チャージバック、不正決済、さらには国ごとの規制など、販売国によって注意点は多岐にわたります。
ここでは、導入前に確認しておくべき代表的なリスクとその対策について整理し、安定的な運用につなげるためのポイントをご紹介します。
為替変動リスクと価格設定の見直し
越境ECにおいて現地通貨で販売する場合、為替の変動が収益に与える影響は避けられません。為替レートの変動により、日本円換算での利益は同じ商品でも大きく変動するため、価格設定は定期的に見直す必要があります。
特に円高局面では利益率が下がるおそれがあるため、あらかじめ収益を確保できる価格帯を設けておくことが望ましいといえます。加えて、為替リスクを軽減する手段として、為替予約の活用や多通貨決済に対応したサービスの導入も選択肢となります。
あらかじめ市場や通貨ごとのリスクを想定した体制を整えておくことで、為替の影響を最小限に抑え、より安定した収益の確保につなげられます。
関税・輸入税による追加コストの影響
越境ECでは、商品の価格とは別に関税や輸入税が発生するケースが多く、これらの追加負担は購入者の購買意欲に影響を与える要因となります。関税率や免税の適用範囲は国ごとに異なるため、対象国の税制をあらかじめ把握しておくことが欠かせません。
とくに消費者が関税の存在を認識していない場合、商品到着時に予想外の費用が発生し、返品やキャンセルにつながるおそれがあります。こうしたトラブルを避けるには、商品ページ上で関税がかかる可能性や概算額を明記し、価格に対する透明性を高めることが重要です。
さらに、関税の有無や購入者・販売者いずれがその費用を負担するのかを明示することで、誤解の防止にも役立ちます。
チャージバック・不正決済への備え
越境ECでは、クレジットカードの不正利用やチャージバックといったリスクへの対応が欠かせません。特に海外発行カードを利用した取引では、不正決済の検出が難しく、購入者が身に覚えのない取引として否認すれば、売上が取り消される事態も起こり得ます。
これを防ぐには、3Dセキュアなどの本人認証機能を備えた決済手段の導入が効果的です。加えて、信頼性の高い決済代行会社を選定し、PCI DSSなど国際的なセキュリティ基準に準拠した運用体制を整える必要があります。
不審な注文を自動で検知する仕組みや、注文履歴の保存などの内部対策も講じることで、リスクを抑えつつ安定した運営が実現します。
国による規制やライセンス要件の違い
越境ECでは、販売先の国や地域ごとに異なる決済関連の法規制やライセンス要件に注意を払う必要があります。なかには、オンライン決済サービスの提供にあたって金融ライセンスの取得が義務づけられている国もあり、未対応のまま運用を開始すると、サービス停止や法的トラブルに発展するおそれがあります。
加えて、個人情報保護やマネーロンダリング対策(AML)に関する規制も国によって異なるため、決済データの管理方法にも十分な配慮が求められます。こうしたリスクを避けるためには、事前にターゲット国の法制度を調査し現地事情に精通した決済代行サービスや法務パートナーの力を借りることが有効です。
その結果、安全かつ円滑な決済環境を整えることが可能になります。
おすすめの越境EC決済サービス・代行会社4選

越境ECを展開するうえで、自社のターゲット市場に適した決済手段を選ぶことは、売上や顧客満足度を左右する重要な要素です。とはいえ、各国の主流決済に幅広く対応し、コストや運用負担を抑えられるサービスを見極めるのは簡単ではありません。
ここでは、信頼性・対応力・導入のしやすさの3点を軸に、特におすすめの決済サービス・代行会社を4つご紹介します。
SBペイメントサービス:国内外に強い大手の安心感

SBペイメントサービスは、ソフトバンクグループに属する企業として、高い信頼性と安定した決済代行サービスを展開しています。越境ECにおいても、AlipayやWeChat Pay、銀聯カード、PayPalなど主要な海外決済手段に対応し、販売先の国や地域に合わせた柔軟な運用が可能です。
セキュリティ面では、国際的な基準であるPCI DSSに準拠しており、不正利用や情報漏洩への対策も徹底されています。さらに、複数の決済手段を一括で管理できるため、事業者にかかる運用負担の軽減にもつながります。
shopifyなどのカートシステムとの連携実績も豊富で、導入から運用までをスムーズに支援してくれる点も魅力です。こうした国内外での実績と対応力を備えており、初めて越境ECに挑戦する企業にとっても安心して導入できるサービスといえるでしょう。
参考:SBペイメントサービス
DGフィナンシャルテクノロジー(旧ベリトランス):多通貨・中国系決済に強み
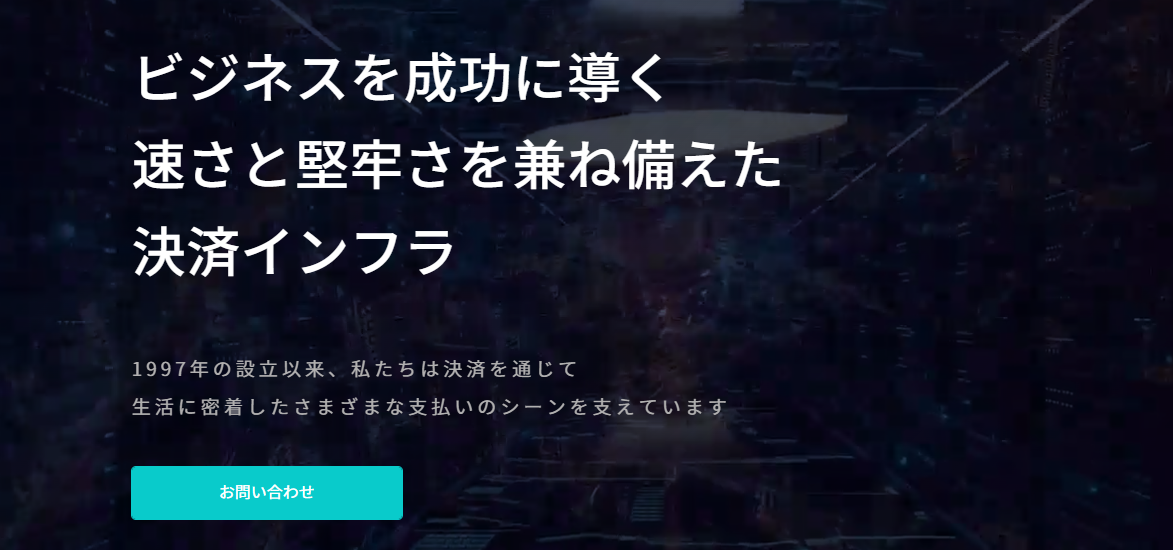
DGフィナンシャルテクノロジー(旧ベリトランス)は、越境ECにおける多通貨対応と中国系決済に強みを持つ決済代行サービスです。特に中国市場への対応力が高く、銀聯ネット決済やAlipay(アリペイ)国際決済を通じて、中国人顧客のニーズに的確に応えています。
加えて、PayPalや多通貨クレジットカードにも対応しており、海外の利用者が自国通貨で違和感なく支払いを完了できる点も魅力です。こうした機能により、EC事業者側は外貨換算の手間を省きながら、日本円での一括入金が実現します。
さらに、国際セキュリティ基準を満たした堅牢な決済環境を整備しており日本語対応の管理画面やサポート体制も用意されています。そのため、越境ECが初めての企業でも、安心して導入できるサービスとして高く評価されています。
NTTデータ:アジア展開に特化した堅実な代行サービス

NTTデータは、アジア各国で越境ECを展開しようとする企業にとって、信頼性の高い決済代行サービスを提供しています。グローバル決済ゲートウェイを通じて、クレジットカードやコード決済、オンラインバンキングなど、各国で主流となっている手段に対応できるシングルAPIを用意しており、開発コストの抑制や運用負担の軽減につながります。
さらに、中国のAlipayや銀聯カードに加え、韓国・台湾・東南アジアのローカル決済にも強みがあり、現地パートナーとの連携によって柔軟なカスタマイズも可能です。多言語対応のサポート体制が整っているため、導入から運用まで一貫してスムーズに進めることができます。アジア市場への本格的な進出を目指す企業にとって、有力な選択肢といえるでしょう。
参考:NTTデータ
WorldShoppingBIZ:中小事業者でも導入しやすいEC支援型サービス
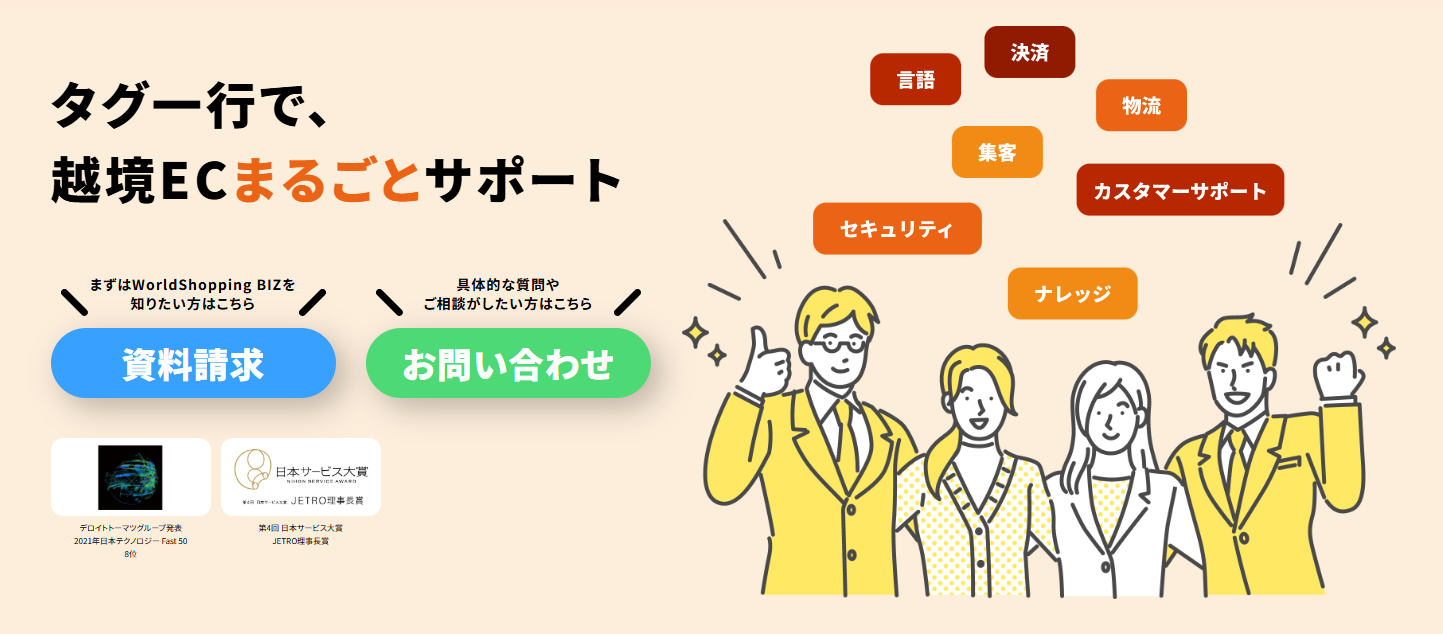
WorldShoppingBIZは、越境ECの導入ハードルを下げたい中小事業者にとって最適なEC支援型サービスです。タグを一行追加するだけで、自社ECサイトに多言語・多通貨対応の購入機能を組み込めるため、既存のサイトをそのまま海外展開に活用できます。
決済手段としては、VISA・Mastercard・American Expressに加え、PayPal、Amazon Pay、Alipay、銀聯カードなど各国で主流の方法を幅広くカバーしています。アジア圏をはじめ、さまざまな地域のユーザーに対応可能です。
さらに、受注・配送・カスタマー対応まですべてワンストップで代行されるため、少人数の体制でも無理なく運用できます。導入コストを抑えながら迅速に越境ECをスタートさせたい企業にとって、WorldShoppingBIZは頼れる選択肢となるでしょう。
越境ECで成功を目指すうえでは、決済手段の最適化と同時に、現地市場に精通したコンサルタントの支援を得ることも重要です。戦略立案から実行まで一貫してサポートしてくれる企業を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
まとめ:最適な決済導入で越境ECを成功に導こう
越境ECを成功させるには、ターゲット国の決済習慣に合った方法を採用することが欠かせません。クレジットカードやPayPalに加え、現地で親しまれている電子マネーやネットバンキングなども取り入れることで、購入の離脱を防ぎ、顧客に安心感を与える取引環境を構築できます。
さらに、手数料や入金サイクル、セキュリティといった運用面に配慮しながら、信頼性の高い決済代行サービスを選定すれば、業務の効率化も期待できます。自社の商品特性や販売戦略を見極めたうえで、最適な決済体制を整えることが、グローバル市場における収益拡大の重要な一歩となるでしょう。