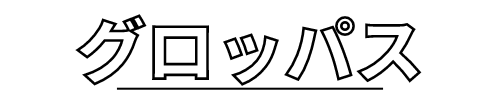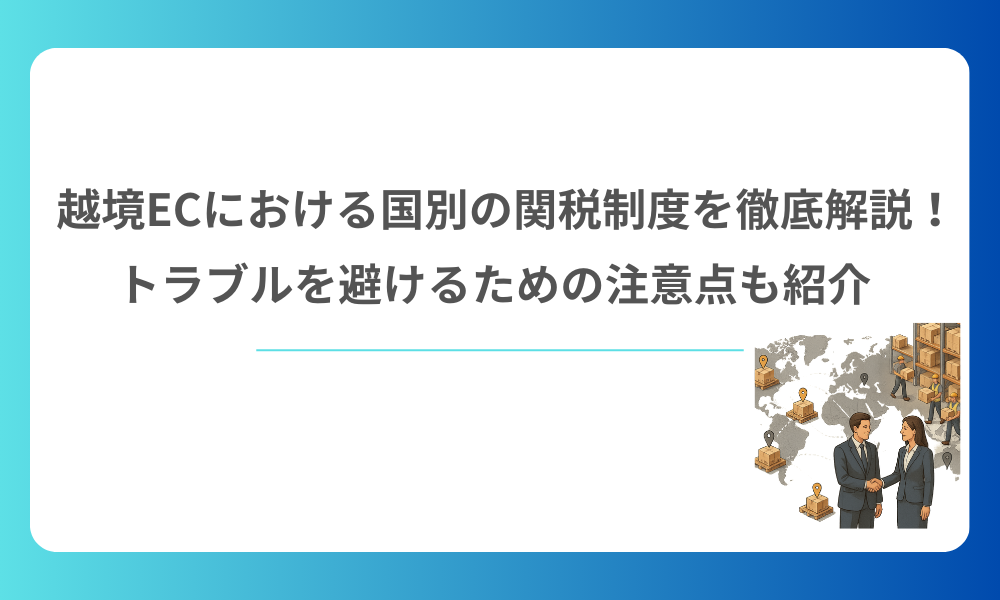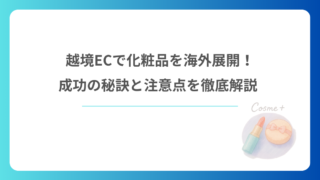越境ECを始めるうえで避けて通れないのが「関税」の問題です。国ごとに制度や税率が異なるため、正確な情報を事前に把握しておかなければ、販売価格の設定や利益率の確保に支障が生じかねません。加えて、対応を誤れば顧客からの信頼を損なう要因にもなります。
そこで今回は、主要国の関税制度をわかりやすく整理し、トラブルを未然に防ぐためのポイントも紹介いたします。
関税とは?

越境ECを行うにあたって避けて通れないのが「関税」の理解です。国ごとに制度や税率が異なる関税は、販売価格や利益率、さらには取引の信頼性にも大きく影響します。
まずは関税の基本を押さえ、どのような仕組みで課税されるのか、そもそもどのような目的で設けられているのかを確認しておきましょう。
関税の基本的な仕組み
関税とは、海外から輸入される商品に対して課される税金のことを指します。これは各国の制度に基づいて細かく分類され、商品ごとに「HSコード(国際統一商品分類)」を用いて税率が決定されます。
税のかけ方には、商品の価格に応じて課す「従価税」、数量や重量に応じて課す「従量税」、その両方を組み合わせた「混合税」などが存在します。税率には、各国が定める「国定税率」のほか、WTO加盟国間などの協定に基づく「協定税率」があり、状況に応じて適用される仕組みです。
越境ECを行う際には、取り扱う商品がどの分類・税率に該当するかを事前に確認し、それに応じた販売戦略を立てる必要があります。適切な対応を怠ると、販売価格や利益に影響が及ぶため、制度の理解と事前準備が欠かせません。
関税の目的
関税の目的は、海外からの輸入品が自国経済に与える悪影響を抑えることにあります。とくに、安価な海外製品が大量に流入した場合、価格差によって国内企業の競争力が低下するおそれがあるため、関税によって輸入価格を調整し、国内産業を保護することが第一の狙いです。
また、関税は政府にとって重要な財源のひとつであり、国の歳入を確保する役割も担っています。加えて、不当な安値で輸出されるダンピング品に対しては、追加の関税(アンチ・ダンピング関税)を課すことにより、国際的な取引の公正性を守る制度的手段としても機能しています。
越境ECで関税が重要な理由

越境ECで関税が重視される理由は、販売価格や利益率にとどまらず、顧客体験全体に深く関わるためです。国によって制度や税率が異なる関税は、商品の価格競争力を左右し、対応を誤ると返品や受取拒否といったトラブルを引き起こしかねません。
とくに、関税の負担者や適用税率についての情報が購入前に示されていない場合、購入者との信頼関係が損なわれるリスクがあります。
そのため、各国の関税制度を事前に把握したうえで、自社商品の分類と適用税率を明確にし、販売ページに関税に関する説明を記載しておく必要があります。関税への対応は、越境ECの成否を分ける重要な要素となります。
国別に見る越境ECの関税制度

越境ECを成功させるには、販売先ごとの関税制度を理解することが不可欠です。関税の有無や発生基準、税率、通関の特徴は国によって大きく異なり、誤認すればトラブルの原因にもなりかねません。
ここではアメリカ、中国、韓国など主要国の関税制度について、注意点とともに詳しく解説していきます。
| 国名 | 関税の有無 | 関税発生の基準額 | 主な対象品目 | 関税率の目安 | 税関通過の特徴 | 特有の注意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | あり | 800米ドル以下は免税 | 衣類、化粧品、家電など | 約5〜20% | 小口貨物は簡易通関 | HTSコードに基づく分類が厳格。FTA品目に注意 |
| 中国 | あり | 行郵税:1,000元以下かつ税額50元未満 | IT機器、食品、高級品など | 13〜50%(行郵税) | 通常通関は比較的簡易(直送) | 越境EC総合税と行郵税の使い分けが必要 |
| 韓国 | あり | 150米ドル未満は免税 | アパレル、食品、家電など | 約5〜40% | HSコードによる分類・原産地証明を要す | FTAによる税率優遇があるが、VAT10%に注意 |
| 台湾 | あり | 2,000台湾ドル以下は免税 | 健康食品、化粧品、日用品 | 約5〜30% | CCCコードの確認が必要 | 関税に加え営業税(VAT)5%も考慮が必要 |
| シンガポール | 一部のみ | 明確な金額基準なし(少額取引は非課税傾向) | 酒類、タバコなどを除きほぼ非課税 | 非課税が基本(例外あり) | 電子的通関が主流でスムーズ | GST(物品サービス税)8%が400SGD以上で課税対象 |
| インドネシア | あり | 免税基準の明記なし | 衣料品、家電、化粧品など | 10〜70%が目安 | CIF価格ベースで税額算定 | LST(贅沢品税)とVAT10%も別途必要 |
| マレーシア | あり | 明確な免税基準なし | 衣料品、食品、電化製品など | 0〜60%(品目による) | 比較的スムーズ | SST(売上・サービス税)6%も加味が必要 |
アメリカにおける関税制度
アメリカでは、基本的に輸入品に関税が課されており、日本からの商品には「一般税率」が適用されます。個人輸入に限っては、商品の価格が800ドル以下であれば関税の対象外となります。
対象となる品目は化粧品や衣類、家電など多岐にわたり、越境ECで扱われる商品も例外ではありません。関税率は品目や原産国、価格により異なり、平均すると5~20%程度とされています。
また、2,500ドル以下の小口貨物であれば、簡易な手続きによる通関が可能な場合もあります。アメリカでは「HTSコード」に基づいて商品が細かく分類されており、分類の誤りが追加課税の原因となるため、事前確認が重要です。
さらに、特定の品目には自由貿易協定(FTA)による優遇税率が適用されることがあり、これらの対象商品についても把握しておく必要があります。
中国における関税制度
中国では輸入品に対して関税が課されており、越境ECにおいては「行郵税」と「越境EC総合税」が中心的な制度です。
行郵税は、個人宛てに商品を直接配送するモデルに適用され、1回の注文金額が1,000元以下かつ税額が50元未満の場合は免税となります。対象品目はIT機器や食品、衣料品、高級品などで、税率は13〜50%の範囲に設定されています。
一方、保税倉庫を通じた取引では越境EC総合税が適用され、税率は9.1〜23.1%ですが、関税そのものは免除されます。なお、1回の注文が5,000元以下かつ年間で26,000元を超えないことが条件です。
通関においては、行郵税モデルであれば比較的簡易に手続きが進みますが、総合税の適用には事前登録や対象商品の制限といった要件があります。
また、中国独自の制度として、取扱商品があらかじめ定められた「ポジティブリスト」に含まれている必要がある点や、最恵国税率や特恵税率など複数の税率体系が存在する点にも留意しなければなりません。
こうした特徴を十分に理解し、適切な税制対応を行うことが越境EC展開の成功につながります。
越境ECで中国市場に進出する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
韓国における関税制度
韓国では輸入品に関税が課されており、価格に応じた従価税や数量に基づく従量税、またはそれらを組み合わせた混合税が適用されます。免税の対象となる基準額(De Minimis)は150ドル未満と定められており、それを超えると課税対象となります。
対象品目には化粧品やアパレル、食品、家電などがあり、品目ごとの関税率はおおむね5~40%の範囲に収まります。
通関手続きは比較的円滑に進みますが、HSコードによる分類や原産地証明の提出が必要になることもあります。
さらに、韓国ではFTA締結国との間で関税が軽減・免除されるため、協定税率が適用されるかどうかを事前に確認することが重要です。加えて、輸入時には10%の付加価値税(VAT)が課される点にも留意が求められます。
台湾における関税制度
台湾では輸入品に関税が課されており、価格に応じた従価税、数量や重量に基づく従量税、またはその両方を組み合わせた混合税が適用されます。
免税の基準は2,000台湾ドル(約1万円)以下で、それを超える場合には課税対象となります。対象品目は化粧品や健康食品、日用品など越境ECで人気の高い商品が多く、関税率は品目ごとに異なり、一般的には5~30%の範囲内です。
通関手続きは比較的スムーズであり、日本は「カラム1」に分類されている優遇国として、他国よりも低い税率が適用されます。
さらに台湾では、HSコードに加えて独自のCCCコードによる分類も用いられているため、商品の正確なコード確認が重要です。関税とは別に5%の営業税(VAT)も課されるため、販売価格の設定時にはこれら両方の負担を見越した対応が求められます。
シンガポールにおける関税制度
シンガポールでは、原則として輸入品に関税は課されず、大半の商品が非課税となります。関税が適用されるのは、ビールやタバコ、アルコール類など一部の品目に限られており、課税基準は商品価格や数量に基づいて設定されています。
越境ECで多く扱われる化粧品や衣料品、日用品などは関税の対象外に分類されます。免税基準額(De Minimis)は公式には定められていませんが、少額商品の輸入については一般的に円滑に進みます。
通関手続きも効率的に運用されており、オンラインシステムの導入によって迅速な処理が可能です。
一方で、関税とは別に物品・サービス税(GST)が輸入時に課税される点には注意が必要です。現行の税率は8%で、今後の引き上げも予定されています。GSTは、取引額が400シンガポールドルを超える場合に適用されます。
インドネシアにおける関税制度
インドネシアでは輸入品に対して原則として関税が課され、ほとんどの商品が課税対象となります。免税となる明確な基準(De Minimis)は設けられておらず、すべての輸入品に課税される可能性があります。
対象品目はアパレル、家電、日用品、化粧品など多岐にわたり、関税率は品目によって0〜200%と幅があり、必需品では10~40%、一般品では50~70%が目安です。
税関手続きではCIF価格(商品価格に運賃と保険料を加えた金額)を基に申告を行い、正確なHSコードの分類が求められます。
さらに、輸入時には付加価値税(VAT)10%が課されるほか、対象商品によっては贅沢品税(LST)も加算されるため、価格設定にはそれらの税負担を含めて検討する必要があります。
マレーシアにおける関税制度
マレーシアでは輸入品に関税が課されており、多くの品目が従価税の対象となります。免税基準額(De Minimis)は明確に定められておらず、少額であっても課税される可能性があるため注意が必要です。
対象となる商品には化粧品や衣料品、食品、電化製品などが含まれ、関税率は品目ごとに異なり、0〜60%の範囲で設定されています。
通関手続きは比較的スムーズで、HSコードによる分類に基づき税率が適用されます。日本からの輸入品には、JMEPA(日マレーシア経済連携協定)やAJCEP(ASEAN日本包括的経済連携)の適用により、関税の減免や免除が受けられる場合があります。
さらに、マレーシアでは関税に加え、6%の売上・サービス税(SST)も課されるため、価格設定時には両方のコストを見込んだ対応が求められます。
越境ECで化粧品を海外展開する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
越境ECにおける日本の消費税との関係

越境ECでは、販売先となる海外の税制度だけでなく、日本国内での消費税の取り扱いも理解しておく必要があります。とくに輸出取引に該当する場合、日本の消費税が免除されるほか、一定条件を満たせば還付も受けられます。
ここでは、免税の仕組みや還付制度の概要について確認しておきましょう。
輸出時の免税措置について
日本では、商品を海外へ輸出する際、原則として消費税が課されない「輸出免税制度」が適用されます。越境ECによる販売もこの制度の対象となるため、国内で発生する消費税を回避できる仕組みです。
免税を受けるには、輸出取引であることを示す書類(輸出許可書など)を用意し、税務署の指導に基づいて正しく保管する必要があります。とくに個人事業主や中小企業にとっては、価格に含まれる税負担を抑えられる点で有利に働きます。
免税措置の活用にあたっては、要件や申請手続きの流れをあらかじめ理解しておくことが、今後の越境EC展開に向けた準備として欠かせません。
課税事業者なら還付の対象に
越境ECにおいて商品を輸出する場合、日本国内の消費税は原則として免税となります。ただし、仕入れ時などにすでに支払った消費税については、一定の条件を満たせば還付を受けられます。
そのためには、まず「課税事業者」であることが前提となります。対象は、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。さらに、消費税の申告にあたっては「原則課税方式」を選択している必要があり、「簡易課税方式」を利用している場合は還付の対象外です。
還付を受けるには、確定申告書に加え、仕入控除税額明細書や輸出許可書などの書類を準備し、所轄の税務署へ提出しなければなりません。
輸出取引が増えるほど、還付による金額の差は大きくなります。したがって、越境ECを継続的に展開するのであれば、早い段階で課税事業者としての登録と、原則課税方式への切り替えを視野に入れることが重要です。
越境ECで関税トラブルを避けるための注意点

越境ECでは、関税の誤認や説明不足が原因で、返品・受取拒否といったトラブルが発生することがあります。こうしたリスクを回避するには、取り扱い商品の分類や税率の確認をはじめ、ECサイト上での明示や制度改正への対応、VATなど周辺税制への理解も欠かせません。
ここでは、越境ECで関税トラブルを避けるために意識することを解説します。
取り扱い商品の分類と関税率を確認する
越境ECにおいては、取り扱う商品の分類と関税率の把握が非常に重要です。各国では「HSコード(国際統一商品分類)」に基づいて商品が詳細に分類され、それぞれに異なる税率が設定されています。
関税の形態には、価格に対する「従価税」、数量や重量に応じた「従量税」、そして両者を組み合わせた「混合税」があり、商品の性質により適用方法が異なります。
まずは自社商品に該当するHSコードを特定し、販売対象国の関税データベースやFedExが提供する「WorldTariff」などを利用して該当税率を確認してください。分類の誤りは税関でのトラブルや追加課税につながるおそれがあるため、事前の精査が欠かせません。商品登録や価格設計の段階から、関税の影響を踏まえた計画を立てることが成功の鍵となります。
関税の有無をサイト上で明記する
越境ECでは、購入前に関税の有無を明示することが、取引トラブルを防ぐうえで極めて重要です。国ごとに課税の有無や税率が異なるため、購入者が予期しないコストに戸惑うケースも見受けられます。
とくに関税に関する情報が不十分な場合、受取拒否や返品、評価の低下につながるおそれがあります。こうしたリスクを避けるには、商品ページやFAQで「関税が発生する可能性がある」「関税は購入者負担または出品者負担」などの情報を記載し、明確な説明を加えることが大切です。
加えて、可能であれば関税の目安額も掲載し、購入前の判断材料として提供すると、より丁寧な対応につながります。こうした配慮が購入者の安心感を生み、信頼関係の構築に貢献します。
法改正や通関制度の最新情報をチェックする
越境ECでは、各国の法改正や通関制度の動向に常に注意を払う必要があります。関税率や免税枠の見直し、通関手続きの電子化といった変更は、突如として実施される場合があり、事前に把握していなければ予期せぬコスト増や納期の遅延につながる恐れがあります。
特に輸出入に関する規制は政治や経済の影響を受けやすく、短期間で状況が変わることも少なくありません。対策としては、政府機関の公式サイトや商工会議所、JETRO、現地の通関業者からの通知を定期的に確認し、常に最新の情報を得ておくことが求められます。
こうした柔軟な対応力を備えることで、取引の安定性と信頼性を保つことができます。
付加価値税(VAT)に注意する
越境ECでは、関税に加えて付加価値税(VAT)への対応も重要です。VATは日本の消費税に似た間接税で、商品やサービスの消費時に課されます。
EU諸国や東南アジアの多くでは導入が義務づけられており、国ごとに税率が異なります。たとえばEUでは最低15%以上、インドネシアや台湾ではおおむね10%前後とされています。関税が免除される取引でも、VATの対象となることがあるため見落としは避けなければなりません。
販売価格を設定する際には、関税だけでなくVATも加味した総額での表示を意識し、ECサイト上でわかりやすく案内することがトラブルの防止につながります。現地の税制度を正しく理解し、適切な価格設計と納税対応を行うことが、円滑な販売運営に不可欠です。
まとめ:関税対応を万全にして越境ECを成功させよう
越境ECを成功へと導くには、各国の関税制度に対する理解と的確な対応が不可欠です。関税率や免税基準、VAT(付加価値税)の有無は国によって異なり、販売価格や利益構造に直接影響を及ぼします。加えて、関税の負担者や課税額が明示されていない状態で取引を行えば、受取拒否や返品、苦情といったトラブルを招く恐れもあります。
こうしたリスクを回避するためには、事前に商品の関税率を正確に把握し、ECサイト上で必要な情報を明確に提示することが求められます。加えて、法改正や通関制度の変更にも素早く対応できるよう、社内体制を整えることも重要です。信頼できる通関業者との連携を視野に入れることで、実務面の負担を軽減できる可能性もあります。
税制リスクに備えた関税対応を徹底することで、顧客との信頼関係を築きながら、スムーズな国際取引を実現する土台が整います。越境ECの成否は、このような基本対応の積み重ねにかかっているといえるでしょう。
越境ECでは関税対応だけでなく、市場調査や販売戦略の立案など、専門的な支援も重要です。実務面に不安がある場合は、コンサルティング会社の活用も視野に入れてみましょう。