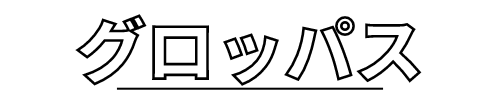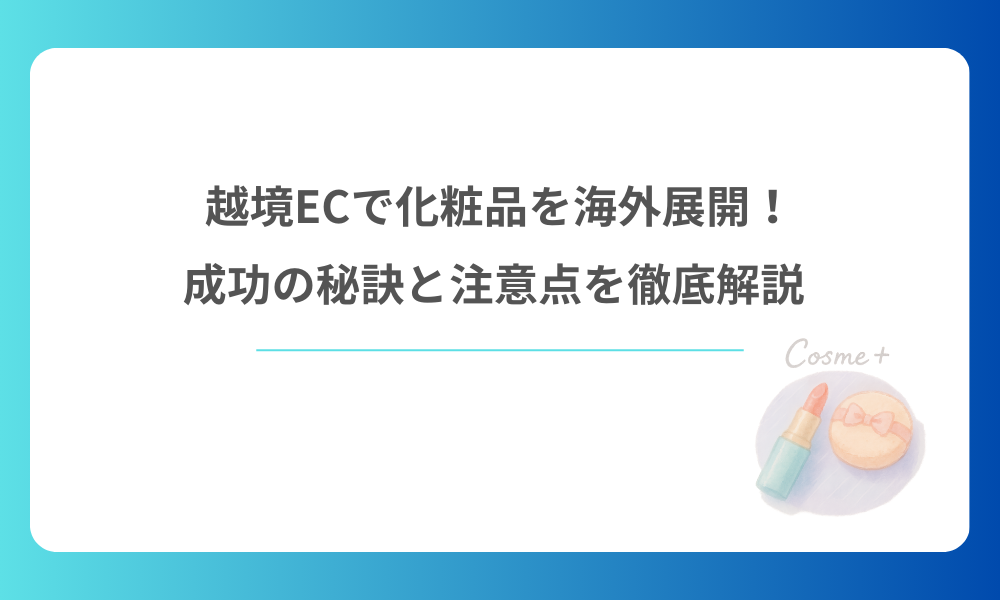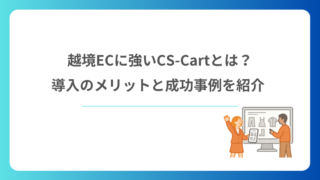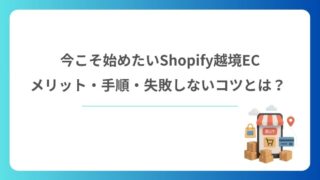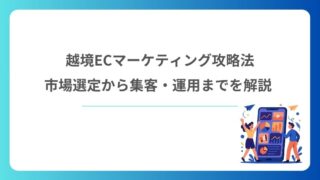国内市場の成熟化が進み、インバウンド需要の減少が懸念される現在、日本の化粧品ブランドにとって越境ECは有望な成長手段として注目を集めています。とくに東南アジアや中国では、日本製の高品質かつ信頼性の高い化粧品が根強い人気を保ち、ECを介した継続的な販売機会の創出が進んでいます。
そこで今回は、化粧品の越境ECに取り組む際の利点や成功事例に加え、実践的な販売戦略や各国規制への対応についても幅広く解説し、海外展開を目指すブランドに向けた実用的なヒントをお届けします。
なぜ今「化粧品×越境EC」が注目されているのか

国内市場の成熟やインバウンド需要の減少が進むなか、多くの日本ブランドが新たな成長機会として海外展開を模索しています。その中でも越境ECは、有力な販路として注目を集めています。とりわけ化粧品は、日本製の高品質や安全性への信頼感から国際的にも高く評価され、アジア圏を中心に需要の拡大が続いています。
ここでは、化粧品と越境ECが今なぜ注目を浴びているのか、その背景を三つの視点からひも解いていきます。
日本製化粧品は「高品質・安心」で世界中から支持されている
日本製の化粧品は、「高品質で安心して使えるブランド」として世界中の消費者から厚い信頼を得ています。厳しい製造基準と徹底した品質管理のもとに生み出される製品は、肌への優しさや機能性、安全性の面で高く評価されており、とくに敏感肌の人や自然由来の成分を重視する層に根強い人気があります。
近年では、訪日外国人が帰国後に越境ECを通じて同じ商品を購入する動きも広がりを見せています。こうした背景のもと、日本市場が成熟する一方で海外からの需要は拡大を続けており、越境ECは日本ブランドの魅力を届ける手段として、より重要性を増しています。
コロナ禍以降、世界的にEC需要が急拡大したため
新型コロナウイルスの影響を受け、世界中で生活様式が大きく変化しました。外出の制限や店舗営業への制約が続いたことで、消費者の購買行動は急速にオンラインへと移行し、EC市場全体が著しく成長しました。化粧品分野も例外ではなく、対面での購入機会が減少するなかで、越境ECを通じた需要が高まっています。とくに日本製品は品質への信頼から選ばれる傾向が強く、自宅にいながら簡単に購入できる手段として越境ECの活用が広がりました。
この変化は一時的な対応にとどまらず、消費行動の新たなスタンダードを生み出す転換点となっています。今後も、オンライン販売を基盤とした海外展開は、確かな成長の道筋として期待されるでしょう。
中国や東南アジアの若年層を中心に「日本のコスメ」が人気
近年、中国や東南アジアの若年層の間で「日本のコスメ」への関心が高まっています。特に20~30代の女性からは、美白や保湿、肌への優しさといった品質の高さが評価され、「安心して使える日本ブランド」として信頼を集めています。
また、SNSやライブコマースを活用したプロモーションは、現地ユーザーとの接点を築くうえで有効な手段となっており、KOL(キーオピニオンリーダー)の発信力も大きな影響を与えています。さらに、インバウンド需要を通じて日本商品に触れた消費者が、帰国後に越境ECを利用してリピート購入する傾向も定着しつつあります。
今後は、若年層のライフスタイルに寄り添うアプローチが、日本ブランドの成長を左右する要因となるでしょう。
越境EC化粧品の狙い目市場とその特徴

越境ECで化粧品を販売するには、各国の市場特性を的確に捉えた戦略設計が求められます。中国や東南アジア、アメリカといった地域では、需要の傾向や消費者の購買行動に違いが見られるため、自社商品の特性と調和する市場を見極めることが重要です。どの国を優先すべきかを判断するには、現地の文化や流通環境の理解が欠かせません。
ここでは、注目度の高い主要な5市場と、それぞれに見られる特徴について解説します。
中国市場|爆発的な需要とKOLマーケティングの有効性
中国市場は、越境ECにおいて圧倒的な規模と成長の余地を備えています。なかでも日本製の化粧品は「安全性」や「高品質」といった面が評価されており、特に20〜30代の女性から高い支持を得ています。中でも注目されるのが、ライブコマースやKOL(キーオピニオンリーダー)を活用した販売戦略です。
影響力のあるインフルエンサーが商品を紹介することで、短時間で売上が急増する現象も珍しくありません。実際に「フジコポムポムパウダー」などは、KOL施策によって中国市場で品薄となるほどの反響を呼びました。こうした事例からもわかるように、中国で成果を上げるには、現地の消費文化に適応したマーケティングと、信頼性の高いKOLの活用が極めて重要だといえるでしょう。
越境ECで中国市場に参入する方法については以下の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。
東南アジア市場|モバイルECが急成長中の注目エリア
東南アジアは、経済成長の加速とスマートフォンの高い普及率を背景に、モバイルECを軸とした越境ECの成長が期待される地域です。インドネシアやベトナム、フィリピンでは、若年層の割合が多く、SNSやライブ配信を通じた購買行動が定着しつつあります。
ShopeeやLazadaといった現地のECプラットフォームが大きな影響力を持ち、日本製の化粧品は「信頼できるブランド」として高い評価を受けています。さらに、セールやキャンペーンに対する反応も良く、購買意欲の高さがうかがえます。こうした特性を理解し、現地の消費傾向に即した柔軟な戦略を展開することが、成果につながるでしょう。
アメリカ市場|単価・購入頻度ともに高く安定したニーズ
アメリカ市場は、越境ECにおける有力な販売先として高い収益性が期待される魅力的な地域です。とくに化粧品分野では、1回の購入あたりの単価が高く、定期便やギフトとしての需要も根強く存在しています。このような背景から、継続的な売上につながりやすいのが特長です。
さらに、ECの利用が日常に根付いており、AmazonやWalmartといった大手モールを活用すれば、比較的短期間で販路を築ける可能性があります。加えて、オーガニックやナチュラル志向が強まるなかで、日本製の高品質かつ安心な化粧品は高い評価を受けやすい状況にあります。
FDAの規制への対応は求められるものの、その制度を正確に理解し、適切に対処することで、大規模な販路の獲得も十分に狙える市場といえるでしょう。
Amazonの越境ECについては以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
台湾市場|親日的な国民性と日本ブランドへの高評価
台湾市場は、越境ECで化粧品を販売する上で極めて親和性の高い地域です。親日的な国民性に加え、日本製品への強い信頼感が「Made in Japan」の価値を押し上げています。特に敏感肌向けや自然派志向の化粧品は現地でも高く評価され、日常使いとして定着する傾向が見られます。
販売チャネルとしては、ShopeeなどのECモールが主流であり、コンビニ決済や口コミによる購買行動にも配慮した対応が求められます。さらに、東南アジア同様に訪日経験者が多く、帰国後に越境ECを活用して日本製品を再購入する流れも一般化しています。こうした背景から、台湾市場は安定した需要とさらなる拡大の可能性を兼ね備えた有望なターゲットと位置づけられます。
ヨーロッパ市場|高い規制をクリアすれば広がるプレミアム市場
ヨーロッパ市場は、化粧品に対する規制が非常に厳しいことで知られていますが、その基準を満たすことができれば、高価格帯のプレミアム市場に参入できる可能性があります。EUでは、各製品について安全性や成分、製造過程を明記した製品情報ファイル(PIF)の提出が義務付けられ、EU域内に責任者を配置することも要件のひとつです。
このように参入には高いハードルがありますが、それを乗り越えたブランドには、顧客の信頼と継続的な購買が期待されます。さらに、自然派志向やヴィーガン対応、サステナブルな姿勢など、欧州の価値観と親和性の高い日本製品は高く評価されやすく、ブランド戦略を重視した展開にも適しています。長期的な成長を目指すなら、欧州市場は見逃せない重要なターゲットとなるでしょう。
越境ECで化粧品を販売するメリット

日本製の化粧品は、品質や安全性への信頼から海外市場で高く評価されています。近年はECインフラの発展により、越境ECを活用した販売が中小ブランドでも実現しやすくなりました。ここでは、化粧品の越境ECに取り組むことで得られる5つの主なメリットについて詳しく紹介します。
市場規模がグローバルに拡大し続けている
世界的なデジタル化の進展とスマートフォンの普及により、越境ECの市場は着実に拡大しています。特にアジア地域ではECビジネスの成長余地が大きく、日本製化粧品への信頼感から、需要は安定して増加傾向にあります。経済産業省の調査でも、中国や米国における日本製品の購入額は毎年二桁成長を記録しており、中でも化粧品は輸出分野で高い注目を集めています。
さらに、実店舗を構えることなくグローバル市場へ展開できる点も、参入へのハードルを下げる要因となっています。今後は新興国の経済成長に伴い、販路がさらに多様な地域へ広がると見込まれ、越境ECは化粧品ブランドにとって不可欠な成長戦略として位置づけられています。
越境ECの市場規模については以下の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。
低コスト・低リスクでスタートしやすい
越境ECは、現地に店舗を構える必要がないため、初期投資を大幅に削減できる点が大きな魅力です。とくに化粧品分野では、小ロット生産やOEMの活用により、在庫リスクも最小限に抑えられます。さらに、ShopeeやAmazonといった越境ECプラットフォームを活用すれば、サイト構築から決済、物流までを一括して支援してもらえるため、専門知識がなくてもスムーズに参入できます。
「気づけば1週間で出店できた」という事例も存在し、立ち上げのスピード感も大きな利点です。こうした特長から、低リスクで海外展開を目指す中小企業や新興ブランドにとって、越境ECは最適な選択肢と言えるでしょう。
購入単価と頻度が高く収益性が見込める
化粧品は日常的に使用される消耗品であるため、購入頻度が高いことが越境ECにおける大きな強みといえます。特に海外では、単価の高い商品であってもオンラインで積極的に購入される傾向があり、日本製品への信頼感がこうした購買行動を後押ししています。
さらに、品質面で高く評価される日本製の化粧品は、定期購入やギフトとしての需要も高く、リピーターの確保が安定した収益につながります。実際に、SNSやライブコマースで商品を知った消費者が、その場でまとめて購入するケースも見受けられます。継続的な購入が期待できる商材であるからこそ、販売体制を整えることで長期的な収益の確保が可能になります。
グローバル展開によるブランド価値の向上
越境ECを通じた海外進出は、単なる販路の拡大にとどまらず、自社ブランドの価値向上にもつながります。世界各国の消費者に認知されることで、ブランドは「国際的な信頼性」を獲得し、国内外問わず高い評価を得られるようになります。
とくに品質や安全性が重視される化粧品分野においては、海外での販売実績が新たな信用の証となり、他社との差別化にも寄与します。さらに、海外ユーザーによるレビューやSNSでの発信は、ブランドの認知力や説得力を高める大きな要素です。その影響は国内市場にも波及し、ブランドの魅力が再認識されるという好循環を生み出します。
販売チャネルの分散によるリスクヘッジが可能
越境ECの大きな利点の一つに、販売チャネルを分散させることで経営リスクを抑えられる点が挙げられます。国内市場だけに依存している場合、景気の動向や消費者の行動変化が売上に大きく影響します。一方で、海外市場を含む複数の販路を確保しておけば、ある市場が不調でも他の地域で売上を補うことができ、全体の収益を安定させやすくなります。
たとえば、中国市場が規制強化などで一時的に縮小した際でも、東南アジアやアメリカといった他地域に展開していれば、ダメージを最小限にとどめられます。また、自社ECサイトとECモールを併用する手法も、集客方法や顧客層の違いを活かした分散戦略として有効であり、経営の安定性を高める要素となります。
越境ECで化粧品を販売する際の注意点

越境ECは有望な販路である一方、販売先の国や地域によって制度や文化が異なるため、丁寧な対応が必要です。とくに化粧品は規制の対象になりやすく、準備を怠ると販売停止や信頼の失墜を招くおそれもあります。ここでは、化粧品を越境ECで扱う際に意識すべき主な注意点を紹介します。
販売国の法規制や成分表示ルールに注意
越境ECで化粧品を展開する際は、販売対象国ごとの法規制や成分表示ルールを正確に把握することが欠かせません。たとえば中国では「NMPA」申請、アメリカでは「FDA」のガイドライン、EUでは「EU化粧品規則」など、国によって異なる基準が設定されています。
これらに基づき、許可や届出が求められることもあり、成分やパッケージ表示が基準に適合していない場合には販売できないこともあります。さらに、使用成分によっては医薬品とみなされる可能性もあるため、出荷前の事前確認が重要です。スムーズな海外展開を実現するには、各国の制度に精通したうえで、必要に応じて専門家の助言を受けながら対応を進めることが望ましいと言えるでしょう。
翻訳や商品説明の質が売上に直結する
越境ECで化粧品を販売する際には、翻訳や商品説明の質が売上に大きく影響します。どれほど品質の高い製品であっても、説明がわかりにくかったり翻訳に違和感があったりすると、購入意欲を損ねてしまうおそれがあります。
とくに化粧品は、成分や使用感、安全性などへの関心が高いため、正確かつ明瞭な表現が求められます。さらに、現地の文化や購買行動に即したコピーであれば、訴求力を高めることも可能です。機械翻訳では伝わりにくいニュアンスや専門用語は、人の手による翻訳・ローカライズによって適切に伝えられます。
こうした丁寧な情報設計により、消費者からの信頼を獲得し、購入へとつながる導線を築くことができるでしょう。
現地で利用されている決済方法に対応する
越境ECでは、現地で主流とされる決済手段への対応が購入率を左右します。たとえば、中国ではAlipayやWeChat Pay、台湾ではコンビニ決済、アメリカではPayPalやデビットカードが一般的です。このように、日本と同じ方法が通用しないことも多く、ユーザーが慣れた手段で支払えなければ、購入を断念する「カゴ落ち」が発生しやすくなります。
したがって、各国の決済傾向を把握した上で、必要に応じて柔軟に手段を追加する姿勢が求められます。利用者にとって快適な決済環境を整えることは、スムーズな購入体験を支えるだけでなく、ブランドへの信頼にも直結します。
物流・関税・返品処理など運用面の整備が必要
越境ECで化粧品を販売するには、物流・関税・返品対応といった運用体制の整備が欠かせません。各国で関税制度や輸送条件が異なるため、コストや配送日数に差が出やすく、事前の情報収集が不可欠です。加えて、商品未着や破損といったトラブルへの備えとして、返品処理のフローも明確にしておく必要があります。
信頼できる物流パートナーを選定し、関税計算や追跡が可能なシステムを導入すれば、業務効率の向上と顧客満足度の両立が図れます。スムーズな運用を実現するには、商習慣や税制に応じた柔軟な対応力を備えた仕組みづくりが重要です。
自社ECとモール出店、それぞれのリスクを把握
越境ECでは、自社ECとモール出店のいずれか、または両方を選択する必要がありますが、それぞれに特有のリスクが存在します。自社ECは自由度が高く、ブランディングや利益率の面で優れていますが、多言語対応や集客、決済・配送などをすべて自社で対応する必要があり、人的・時間的コストがかかります。
一方、モール出店は初期構築の手間が少なく、集客力のあるプラットフォームを活用できますが、手数料が発生し、自社のブランド力を活かしきれない可能性があります。両者のメリット・デメリットを理解し、自社のリソースや戦略に応じた最適な選択が成功の鍵です。
KOL・インフルエンサー起用時の契約と表現に注意
越境ECを展開する際には、自社ECとモール出店のいずれか、または両方を選ぶ必要があります。それぞれに特有のリスクがあるため、慎重な判断が求められます。自社ECはブランディングや利益率の面で優れ、自由度の高い運営が可能です。
ただし、多言語対応や集客、決済・配送といった運用面をすべて自社で管理しなければならず、人的・時間的な負担が大きくなることもあります。一方、モール出店は構築の手間が少なく、既存の集客基盤を活用しやすい反面、手数料がかかり、ブランドの独自性を打ち出しにくい側面があります。こうした違いを把握したうえで、自社のリソースと事業方針に合った形を選ぶことが成功への近道です。
一部成分は医薬品認定の可能性あり
化粧品の越境ECにおいては、配合されている成分が販売先の国で医薬品として扱われるおそれがあるため、事前の確認が欠かせません。たとえば、日本国内では化粧品とされる成分であっても、中国ではNMPA(国家薬品監督管理局)の認可対象となることがあります。
アメリカにおいても、FDAの薬用化粧品規制に該当し、厳しい審査を求められる場合があります。さらに、「ホワイトニング」や「アンチエイジング」などの効果を明示する表現は、配合成分とともに規制対象とみなされる可能性があります。
仮に医薬品と認定されてしまえば、販売停止や商品回収の対応が求められ、事業に大きな影響を及ぼします。そのため、各国の成分規制や分類基準について十分に調査したうえで、必要に応じて専門家の確認を受ける姿勢が重要です。
化粧品の越境EC販売で注意すべき各国の法規制

越境ECで化粧品を海外に販売する際は、各国の法制度や規制を正確に理解することが不可欠です。成分や表示ルール、輸入時の手続きは国によって大きく異なり、事前準備を怠ると販売停止や信頼の失墜につながるおそれもあります。ここでは主要な販路として注目される地域ごとに、化粧品販売に関する法規制や対応ポイントを整理し、スムーズな市場参入のヒントを紹介します。
中国|NMPA申請・CCC認証など独自規制への対応
中国市場で化粧品を越境ECにより販売するには、NMPA(国家薬品監督管理局)への申請が求められます。これは、製品の成分や製造工程が中国の安全基準を満たしているかを確認する制度であり、スキンケアやヘアケアなど一般的な化粧品も審査対象に含まれます。
申請には「一般申請」と「ファイリング申請」の2種類があり、許可の取得には3〜8カ月程度を要するケースも見られます。加えて、美顔器のような電子機器を含む商品については、CCC認証(中国強制認証制度)が必要となる場合があるため、各製品ごとに確認が欠かせません。
さらに、中国EC法においては、越境EC事業者も輸出入に関する法令を順守する義務があります。たとえば、成分表示の正確性の確保や、中国国内における境内責任者の設置が求められます。こうした規制を正しく理解し、事前に必要な準備を進めることが、中国市場への円滑な参入と継続的な展開において重要な要素となります。
アメリカ|FDAのルールと成分規制の確認が必須
アメリカ市場で化粧品を販売するには、FDA(米国食品医薬品局)の規制を正確に理解し、適切な対応を取ることが不可欠です。アメリカでは一般化粧品と薬用化粧品が明確に分類されており、薬用扱いとなる場合は、成分の事前承認や認証の取得が求められる場合があります。
とくに効果効能を強調した表示は、薬用化粧品とみなされるおそれがあるため、表現内容には慎重な配慮が必要です。さらに、製品ラベルの英語表記や成分リストの整備、国内代理人の設置も義務づけられており、これらに不備があるとリコールや販売停止につながる可能性があります。こうしたリスクを回避するためには、事前に制度の全体像を把握し、専門家の助言を受けながら体制を整えておくことが重要です。
EU|責任者の設置と製品情報ファイルの管理が必須
EU市場で化粧品を販売する際は、「EU化粧品規則」に基づき、EU域内に責任者(Responsible Person)を設ける必要があります。この責任者は、製品がEUの安全基準を満たしているかどうかを確認し、現地当局との連絡や対応も担います。
また、製品ごとに成分や製造工程、安全性評価などを記載した「製品情報ファイル(PIF)」を作成し、保管することも求められています。販売開始前には、EU化粧品通知ポータル(CPNP)への登録が必要であり、監査や不具合発生時には迅速な対応が求められます。現地の法制度に精通したパートナーと連携し、制度に則った正確な準備を整えることが、EU市場への安定的な進出を実現するための重要なステップとなります。
東南アジア諸国|国ごとに異なる認可・輸入要件に注意
東南アジア諸国では、日本製化粧品への関心が高まっている一方で、国ごとに異なる認可や輸入規制への対応が不可欠です。たとえば、インドネシアやマレーシアでは、イスラム圏特有のハラール認証が重要視されています。
さらに、タイやベトナムでは、輸入業者の登録や製品ライセンスの取得が義務付けられる場合も見られます。加えて、ASEAN共通の「化粧品指令」に基づく成分規制や表示ルールが存在し、対応を誤ると販売停止や税関での差し戻しといったリスクが生じるおそれがあります。
これらの法規制は頻繁に改訂されるため、現地事情に精通した専門家やパートナーとの連携を通じて、常に最新の情報を把握することが求められます。確実な制度対応を行うことで、東南アジア市場への継続的かつ安定的な進出が可能となります。
台湾・韓国|比較的参入しやすいが事前確認は必須
台湾や韓国は、日本製化粧品への親和性が高く、越境ECにおいて比較的参入しやすい市場といえます。台湾では親日的な文化背景が根付いており、Shopeeなど現地のECモールも広く普及しています。さらに、コンビニ決済をはじめとする現地の支払い手段に対応すれば、展開のハードルは一段と下がります。韓国市場は成熟しており競合も多いものの、日本製品への信頼感は根強く、安定した需要が見込めます。
両国ともに法規制の難易度は比較的低めですが、輸入にあたっては化粧品の成分規制や表示基準、認可要件をあらかじめ確認しておく必要があります。特に韓国では、薬用効果を訴求する場合には医薬部外品として別途申請が必要になることもあります。こうした制度変更に対しても柔軟に対応できる体制を整えることが、越境ECの継続的な成功に直結します。
越境ECにおける化粧品販売の始め方|2つの出店方法

越境ECで化粧品を販売するには、出店方法の選定が最初の重要なステップです。自社ECサイトの構築か、モール型プラットフォームへの出店か、それぞれに特徴とメリットがあります。ここでは、それぞれの具体的な手順について詳しく解説します。
自社ECサイトを構築して販売する方法と手順
越境ECでの自社化粧品販売を成功させるには、自社ECサイトの構築が有効な選択肢となります。自由なデザインやブランディングが可能で、モール出店よりも中長期的な収益性が見込める点が魅力です。ただし、多言語化や決済・物流対応など、事前準備が求められるため、段階的な手順を把握したうえで慎重に進めることが重要です。
Step1 サイト構築プラットフォームの選定
越境ECで化粧品を販売する際、まず取り組むべきは、適切なサイト構築プラットフォームの選定です。自社でゼロから構築する方法もありますが、多言語対応や各国の決済手段への対応など、技術的な手間が大きく、初心者には負担が大きくなりがちです。
そのため、越境ECに対応したパッケージ型カートやモール型プラットフォームを活用する方が現実的といえます。たとえば、Shopeeのようなモール型であれば短期間で出店でき、出品者向けのサポートも整っています。
これに対し、ブランドの世界観を重視したい場合には、CS-CartやShopifyといったカスタマイズ性の高いプラットフォームが有力な選択肢となるでしょう。自社の戦略やリソースに応じて導入のしやすさや将来的な拡張性を見極めながら、慎重に選定を進める必要があります。
CS-CartやShopifyを活用した越境ECについては以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
Step2 決済・物流・通貨設定などインフラ整備
越境ECにおいて安定的な販売を実現するには、決済や物流、通貨設定といったインフラの整備が重要です。たとえば、決済面では中国のAlipayやアメリカのPayPalなど、各国で普及している手段に対応することで、購入離脱の防止につながります。
物流においては、関税の扱いや配送スピード、返品対応まで見据えたうえで、信頼できるパートナーを選ぶことが欠かせません。Shopeeのようなプラットフォームを利用すれば、現地の配送ネットワークを活用できるため、効率的な運営にも寄与します。
また、現地通貨での価格表示と決済に対応する仕組みも整えておくと安心です。これらのインフラを早い段階で整えることが、スムーズな運用体制と顧客からの信頼の構築につながります。
Step3 商品ページと翻訳の最適化
越境ECで化粧品を販売する際には、商品ページの内容と翻訳の精度が購買率に大きな影響を及ぼします。とくに化粧品は成分や使用感、安全性への関心が高く、曖昧な説明では離脱を招く可能性があります。そのため、原材料や使用方法、効果などを明確かつ丁寧に記載し、現地の消費者が安心して購入できる表現に整える必要があります。
また、自動翻訳に依存せず、専門知識を持つ翻訳者によるローカライズを活用すれば、伝わりやすさが向上します。文化的背景や購買行動を踏まえた表現は、信頼と共感を醸成し、売上の向上にも直結する要素です。最終的には、情報設計の質が購入意欲を左右するため、構成と表現の精度を高める姿勢が重要です。
Step4 マーケティング・集客施策の設計
越境ECで安定した成果を上げるためには、戦略に基づいたマーケティングと集客施策の構築が欠かせません。まずは、ターゲット市場ごとの消費行動を的確に把握し、それに応じたSNSや検索エンジン広告の活用を検討することが重要です。たとえば、中国ではKOL(インフルエンサー)によるライブコマースが効果的とされ、東南アジアではShopeeの大型セールに参加することで認知度の向上が期待できます。
さらに、現地の祝祭日やセール時期に合わせてキャンペーンを設計すれば、購買意欲の喚起につながります。商品レビューやUGC(ユーザー投稿)を通じた信頼形成も見逃せない要素です。自社ECサイトを運営する場合はSEO対策やSNS運用を強化し、モールへの出店時にはプロモーション枠を効果的に活用する必要があります。
越境ECのマーケティング手法については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
海外ECモールに出店して販売する方法と手順
越境ECをスムーズに進めるためには、海外ECモールの特性を理解し、自社商品との相性を見極めたうえで適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、出店先の選定からストア構築、プロモーション施策まで、化粧品ブランドが海外モールで販売を始めるためのステップを具体的に解説します。
Step1 出店先モールの選定(Tmall・Shopee・Amazonなど)
越境ECをモール型で展開する際には、まず出店先の選定が重要なステップとなります。たとえばTmallは中国市場に強く、販売規模の拡大やブランド信頼性を重視する場合に適しています。Shopeeは東南アジアや台湾で圧倒的なシェアを持ち、とくに化粧品分野では日本製品の人気が高いため、相性の良い選択肢といえるでしょう。
さらにAmazonは北米や欧州など広範囲での展開が可能であり、認知度の低いブランドでも比較的スムーズに集客できます。出店先を選ぶ際は、ターゲット国の購買傾向や自社商品の特性、物流・決済インフラの整備状況などを多角的に評価する必要があります。これらを踏まえたうえで、自社に最も適したモールを選定すれば、スムーズな販売体制の構築と継続的な成長につながります。
Step2 出店申請と審査対応
出店先モールが決まった後は、出店申請と審査への対応が必要となります。ShopeeやTmall、Amazonなど、各プラットフォームごとに手続きの流れは異なりますが、一般的には企業情報や商品情報の登録、出店契約への同意、必要書類の提出といった工程を経ることになります。
特に化粧品を取り扱う場合は、販売国ごとに異なる輸出入許可や成分表記のルール、ラベル表示のローカライズ対応が求められることもあるため、事前確認が不可欠です。 さらに、一部のモールでは申請時の審査が厳格であるケースも見られるため、申請前にガイドラインや必要書類の内容を丁寧に確認し、抜け漏れなく準備する姿勢が重要となります。
初めての出店であっても、各モールが提供するサポート機能を活用することで、比較的スムーズな対応が可能です。
Step3 商品登録・ストア構築
商品登録とストア構築は、海外ECモール出店における実務の中心であり、購入率に直結する重要な工程です。化粧品を取り扱う場合には、成分や使用方法、安全性についての説明を正確かつ丁寧に行い、現地の消費者が安心して購入できるよう配慮しなければなりません。さらに、写真のクオリティやストア全体のUI設計も信頼性に大きく影響するため、ブランドの世界観を反映したビジュアル設計が求められます。
Shopeeなどのプラットフォームでは、用意されたテンプレートやサポート機能を活用すれば、初めての出店でも比較的スムーズに設定を進められます。こうした基盤が整うことで、プロモーションやリピート施策への展開も円滑になります。最初の構築段階こそが顧客体験を左右するため、見落としのない設計を心がけることが大切です。顧客視点に立った情報設計と操作性の両面から、質の高いストアを目指しましょう。
Step4 モール内プロモーションとレビュー管理
モール内で実施するプロモーションやレビューの管理は、越境ECにおける販売成果を大きく左右する重要な施策です。ShopeeやTmallなどのプラットフォームでは、ゾロ目セールやフラッシュセールといった大型キャンペーンへの積極的な参加によって、商品認知の拡大と新規顧客の獲得が見込めます。
さらに、レビューは購入の意思決定に強く影響するため、顧客対応を丁寧に行い、肯定的な評価を得ることが求められます。特に化粧品の場合、購入前の不安が生じやすいため、Q&A欄の充実や使用感が伝わる画像の掲載が効果的です。
レビュー投稿を促進するためには、購入後のフォローメッセージの送信や割引特典の提供なども検討するとよいでしょう。こうした取り組みを継続することで、販売実績の向上とリピーターの育成につながります。
越境ECの始め方については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
成功企業に学ぶ!越境EC化粧品販売の実例

越境ECで成果を上げるには、戦略や実行力だけでなく「成功事例から学ぶ姿勢」も重要です。ここでは、日本発の化粧品ブランドがどのように海外展開を成功させたのかを紹介します。具体的な施策や活用したプラットフォーム、プロモーション手法に注目し、今後の自社展開のヒントを見つけてください。
SK-Ⅱ|中国の若年層に絶大な人気を誇る王道ブランド
SK-Ⅱは日本発のスキンケアブランドとして誕生し、現在はP&Gによってグローバルに展開されています。中国市場においては、20〜30代の女性を中心に強い支持を受けており、「高級スキンケアブランド」としての確固たる地位を築いています。ブランドを象徴する独自成分「ピテラ」は、美白や保湿に優れた効果を発揮し、繊細な肌を持つ中国人女性のニーズに合致しています。
また、人気タレントの起用によるCM展開や、SNS・ライブコマースを通じた戦略的なプロモーションにより、若年層から共感と憧れを集めています。さらに、中国本土では多数の店舗を構え、オンラインとオフラインを融合させた購買体験を提供。こうした取り組みにより、SK-Ⅱは中国市場における日本ブランドの成功事例となっており、越境EC参入を目指す企業にとって貴重なモデルケースとなっています。
参考:SK-Ⅱ
ライスフォース|多言語ECサイトとSNS運用で世界展開
ライスフォースは、日本発の薬用スキンケアブランドとして、海外市場における認知を着実に高めています。2010年から越境ECに参入し、現在では世界51カ国への出荷実績を持つまでに成長しました。特徴的なのは、多言語対応の自社ECサイトに加え、FacebookやInstagramを活用したSNSマーケティングを積極的に展開している点です。
ターゲット層は30〜50代の女性であり、日常生活や旅行、食に関連した親しみやすいコンテンツを通じて共感を呼び、着実にファンを増やしています。さらに、各国のホテルやスパでアメニティを展開し、ブランドの認知拡大を図っています。
ユーザー生成コンテンツ(UGC)をECサイトに組み込むことで、実際の使用感を伝えながら購買へとつなげる導線も整備しました。このように、ライスフォースはストーリーブランディングとSNSを連動させることで、海外展開に成功している好例といえるでしょう。
参考:ライスフォース
BULK HOMME|メンズスキンケアで10カ国以上に進出
BULK HOMME(バルクオム)は、メンズスキンケア市場で急速に存在感を高めた日本発のブランドです。2013年の創業以来、「世界No.1メンズスキンケアブランド」を掲げ、越境ECを起点に海外展開を本格化させました。
現在では中国やアメリカ、フランス、イタリアを含む10カ国以上に販路を築いています。海外ではAmazonなどのモールを活用するほか、美容展示会への出展や現地法人の設立などを通じて、ブランド浸透を図っています。
さらに、SNSやインフルエンサーを活用したマーケティング施策により認知度を高め、実店舗での販売と連動させたオムニチャネル展開を推進しています。男性用スキンケアというニッチ市場を明確に捉えたブランディングにより、成功を収めた代表的な事例といえるでしょう。
参考:BULK HOMME
フジコポンポンパウダー|KOL起用と口コミ効果で一気に拡散
フジコポンポンパウダーは、株式会社かならぼが展開するヘアスタイリング用の化粧品です。中国市場への進出にあたっては、時短や利便性を求める女性層をターゲットに設定し、影響力のあるKOL(キーオピニオンリーダー)を起用した大規模なサンプリング施策を展開しました。
その結果、発売からわずか半年で中国市場において品薄となるほどの人気を集めました。さらに、その後は追加の販促活動を行わずとも、口コミとSNSでの情報拡散により、タイやロサンゼルスなど他国でも売上が自然に拡大していきました。こうした動きは、インフルエンサーを活用したマーケティングと、的確なターゲティング戦略が大きく奏功した事例といえるでしょう。
参考:フジコポンポンパウダー
ヤーマン|Tmall Globalで美顔器を展開し中国市場で躍進
ヤーマンは、美顔器市場における日本発ブランドとして、中国で顕著な成果を挙げています。とくに中国最大級のECプラットフォーム「Tmall Global」では、美顔器カテゴリにおいて6年連続で売上1位を達成しました。主力商品である「Bloom WR STAR」は、ラジオ波とEMSを搭載した高性能モデルとして高く評価されています。
2020年にはKOL「薇娅(VIYA)」を起用したライブコマースで注目を集め、翌年には皮膚科医と連携した専門性の高いライブ配信を展開しました。さらに、累計売上が1億元を超えた実績を持つブランドとして、美顔器カテゴリで唯一「ヤーマン旗艦店」がTmallのランキングに名を連ねました。こうした取り組みは、専門性・信頼性・影響力を兼ね備えた越境ECの成功事例として高く評価されています。
参考:ヤーマン
化粧品越境ECで成功するためのポイントと戦略

越境ECで化粧品販売を成功させるには、各国の文化や消費行動に即した柔軟な戦略設計が欠かせません。ここでは、現地ユーザーとの信頼構築やリピーター獲得、規制対応など、実践的かつ具体的な成功ポイントを5つに分けて解説します。
現地ユーザーに合わせた決済方法を導入する
海外市場で化粧品を販売する際には、現地のユーザーが普段から使い慣れている決済手段に対応することが重要です。たとえば、中国ではAlipayやWeChat Pay、台湾ではコンビニ決済、アメリカではPayPalやクレジットカードの利用が一般的とされています。こうした手段を導入していない場合、購入の意思があっても途中で離脱されるおそれがあります。
ユーザーが安心して決済できる環境を整えることは、購買率の向上だけでなく、ブランドへの信頼を育むうえでも大切です。 Shopeeのような越境ECプラットフォームを活用すれば、各国の主要な決済手段に広く対応でき、参入時のハードルを下げることができます。 越境ECの成功には、ユーザーの視点に立った柔軟な対応が求められます。
マーケティング施策を現地文化に最適化する
越境ECでは、国ごとに異なる文化や価値観を正確に捉えたうえで、マーケティング施策を現地向けに調整する姿勢が欠かせません。たとえば中国では、KOL(インフルエンサー)によるライブ配信型の販売が有効であり、SNSを通じたリアルタイムのやり取りが消費者の購買意欲を引き出す要因となります。
一方、アメリカや欧州においては、自然派志向や倫理的価値への関心が高まっており、ブランドの理念やレビューの活用が評価されています。さらに、宗教や習慣に対する配慮が求められる場面も少なくなく、広告表現や販促施策において慎重な対応が必要です。
こうした背景を踏まえ、各国の消費傾向やトレンドを的確に把握し、それぞれの市場に適したローカライズを進めることが、商品への信頼を育て、ブランド浸透を後押しします。
リピーターを育てる仕組みを設計する
越境ECで安定した売上を実現するには、初回購入だけでなくリピーターを着実に育てる仕組みが重要です。とくに化粧品の場合、使用感や効果が再購入の判断基準となるため、購入後のフォロー体制が鍵を握ります。
たとえば、使用方法や相性の良い製品を紹介するメール配信や、レビュー投稿者へのインセンティブ提供が有効です。さらに、定期購入の提案やリマインド通知の活用、誕生日にあわせたクーポン配信もリピート促進に寄与します。
Shopeeなどの越境ECモールを利用すれば、継続的な接点を通じて顧客との関係を深めることが可能です。こうした取り組みを重ねることで信頼を築き、顧客満足度の向上とともに長期的な関係を育むことができるでしょう。
カスタマーサポート体制の現地化と信頼構築
越境ECで化粧品を販売する際には、現地に即したカスタマーサポートの整備が顧客の信頼を得る鍵となります。化粧品は肌に直接使用するため、購入前に不安や疑問が生じやすい商品です。たとえば、現地の言語による問い合わせ対応や、成分・配送に関する質問への丁寧な説明は、ユーザーの安心感を高め、購入の後押しにつながります。
実際にG.Oホールディングスでは、Shopee出店後に寄せられた成分や配送に関する問い合わせに真摯に対応したことで、顧客からの信頼を着実に築いています。カスタマーサポートの質は、ブランド全体の印象を大きく左右する要素でもあります。
販売国ごとの規制と関税の正確な把握
化粧品の越境ECを成功させるには、販売国ごとの法規制や関税制度を正確に把握する必要があります。たとえば中国では、NMPA(国家薬品監督管理局)への申請に加え、成分表記や境内責任者の設置が義務づけられており、これらを怠ると通関時のトラブルや販売停止につながるおそれがあります。また、関税や消費税の課税ルールも国ごとに異なり、最終的な販売価格や利益率にまで影響が及びます。
EC運営を安定的に継続するためには、各国の最新情報を事前に確認し、専門機関や代行業者の活用を視野に入れることが重要です。こうした対応が、ブランドの信頼維持と継続的な販売基盤の構築につながります。
まとめ|越境ECでの化粧品販売はチャンスが多い今が狙い目
日本製化粧品は、その品質と信頼性の高さから海外消費者の支持を集めており、特にアジア市場では確固たるブランド力を誇っています。近年では、コロナ禍を契機にEC需要が拡大し、越境ECプラットフォームの整備も進んだことで、中小企業であっても海外展開を実現しやすい環境が整いました。さらに、消費者の越境EC利用は今後も増加が見込まれており、まさに今が参入の絶好機といえるでしょう。
もちろん、各国の法規制やローカライズ対応といった事前準備は不可欠です。しかし、それを上回る可能性と成長余地が広がっています。国内市場に課題を感じている事業者にとって、越境ECによる販路拡大は、積極的に検討すべき選択肢となるはずです。